子どもの習い事としてよく名前が挙がる「公文」と「学研」。
似ているようで違いも多く、「うちの子にはどちらが合うんだろう?」と迷う方は少なくありません。
わが家も『ベビーくもん』に通った経験があり、年中になったときは「公文にするか」「学研にするか」で悩みました。
でも実際に比べてみると、公文は宿題の量が多く通う回数も多いのに対して、学研は少人数で柔軟に見てもらえるのが魅力的でした。
最終的に「子どもが楽しく通えること」を優先して、わが家は学研を選ぶことに。
この記事では、ベビーくもんを経て学研に通うことを決めたリアルな体験談と、両社の違いから気づいたことをお伝えします。
ベビーくもん体験談(0歳〜4ヶ月)
わが家がベビーくもんを始めたのは、子どもが生後2ヶ月の頃。
自宅の立て直しを控えていて、その後は実家に一時的に住む予定だったため、限られた4ヶ月間だけの受講になりました。
ベビーくもんは、絵本や歌、カードなどを通して親子の関わりを深めるプログラム。
ただ、通っていた時期はコロナ禍ということもあり、月に1回だけ先生とマンツーマンでお話をする形式でした。
教材の使い方や子どもの成長の話を聞けるのは良かったのですが、だんだんと先生との会話がご自身の生徒さんの自慢話中心になってしまい、私は少しモヤモヤを感じるように…。
さらに、自宅の建て替え後は実家近くの教室に転籍し、完成後にまた戻ってくることも勧められました。
でも正直、「先生との相性が合わないのに続けるのは違うな」と思い、ベビーくもんは4ヶ月で終了することにしました。
学研教室体験談(年中〜継続中)
ベビーくもんをやめたあと、年中になってから学研教室の体験授業を受けました。
そのとき子どもが「字を書きたい」「覚えたい」と自分から言ったこと、さらに「ここに通いたい!」と希望したことが、大きな決め手になりました。
学研は週1回から通うことができると聞き、「負担が少ないのは助かるな」と親としても安心。
さらにネットで調べたところ、宿題の量は公文のおよそ半分程度という情報もあり、「これなら続けやすいかもしれない」と感じました。
実際に通ってみると、先生は子どもの様子を見ながら声をかけてくれ、無理なく進めてくれるスタイル。
少人数の教室なので、子どもものびのびと学べていて、毎回楽しみに通っています。
ただ、年中の途中で一度「辞めたい」と子どもが言ったことがありました。
4ヶ月ほど通った頃で、理由を先生に伝えると「楽しくない」とのこと。
先生はすぐに受け止めてくださり、「どうすれば楽しめるか」を考えて工夫してくれました。
その後、辞めるまでの1ヶ月間は、子どもが楽しめるような進め方をしてくださり、最終日には「辞めたくない、続けたい」と泣いて伝えるほどに変化。
その気持ちを尊重して、今も学研を継続しています。
お迎え時間が少し遅れるときは、折り紙などして遊んでいるみたいです。
学研を年長までにする理由と次の選択肢
学研は子どもに合っていて、楽しそうに通い続けています。
それでもわが家では、小学校に上がるタイミングで学研を一区切りにしようと考えています。
理由のひとつは、小学生になると学研は週2回の通塾になること。
共働きのため、親が毎回送り迎えをするのは難しいと感じています。
もうひとつは、子どもの「次の学び方」を考えているからです。
実は年中のとき、車で40分ほどかかる場所にあるトイズアカデミーJr.(ベビーパーク)の知能向上教室に4ヶ月だけ通ったことがあります。
キャンペーン期間だったので短期間でしたが、内容はとても良く、子どもも楽しく通えました。
ただ、毎週通うには距離がネックになり、続けるのは難しいと判断しました。
最近は、近所の小学生から通える進学塾に能力開発コースがあることを知りました。
ここなら歩いて通える距離で、「思考力・判断力・表現力」を育む学びができそうです。
親の私は、読み書きよりも知育教育にとても興味があり、9歳までに「脳の器の大きさ」が決まるらしく、地頭を良くしたいと考えています。
体験コースは年長時の年明けにしかないため、まだどうするか決めてはいませんが、小学校からはこちらも選択肢に入れたいと考えています。
地頭とは
・本来の思考力や情報処理能力:知識や情報そのものではなく、それらを加工・活用して問題解決に導く能力全般を指します。
・学力や知識とは異なる:学校で習う知識や学力とは区別され、人本来の素養や経験から培われる力です。
・具体的な要素:論理的思考力、発想力、理解力、判断力、洞察力などが挙げられます。
公文と学研の違いを比較してみて
わが家はベビーくもんと学研の両方を経験しましたが、雰囲気や進め方に大きな違いを感じました。
特に「教材の特徴」「宿題の量」「通う回数」「先生のスタイル」は、親として選ぶときの判断材料になりやすい部分です。
公文と学研の比較表
| 項目 | 公文(ベビーくもん含む) | 学研 |
|---|---|---|
| 教材の特徴 | プリント中心。反復練習で力をつけるスタイル。ベビーくもんは絵本・歌・カード教材。 | プリント+教具。遊びを交えて学べる柔軟なスタイル。 |
| 宿題の量 | 多め。毎日プリントをこなす習慣づけが基本。 | 公文の半分程度。宿題の負担が軽く、無理なく続けやすい。 |
| 通う回数 | 基本は週2回。ベビーくもんは月1回面談。 | 週1回または週2回を選べる。家庭の事情に合わせやすい。 |
| 先生のスタイル | 自学自習が基本。先生は採点・フォロー役。相性の影響が大きい。 | 少人数で寄り添い型。子どもの気持ちに合わせて進めてくれる。 |
| 費用目安 | 教科ごとに月7,000円前後。ベビーくもんは月2,200円。 | 週1回:6,600円/週2回:7,700円(教材費込み)。 |
| 雰囲気 | 静かに黙々と取り組む。 | アットホームでのびのび。遊び時間も取り入れることあり。 |
親として感じた選び方のポイント
公文と学研、どちらがいいのかは「子どもの性格や家庭の事情」によって大きく変わると感じました。
実際に両方を経験してみて、わが家が大切だと思ったポイントをまとめます。
Point 1:子どもの性格に合うかどうか
- コツコツ繰り返すのが得意 → 公文向き
- のびのび楽しく学びたい → 学研向き
Point 2:家庭の生活リズムに合うか
- 送り迎えや宿題の量に親が負担を感じないかどうか
- 無理なく続けられる仕組みかどうか
Point 3:先生との相性
- 教材や仕組みがよくても、先生との相性が合わないと続けにくい
- 子どもが「行きたい」と思えるかどうかが一番の基準
体験してわかったメリット・デメリット
公文と学研の両方を経験してみて、それぞれに良い点と大変な点がありました。
わが家の体験をもとに、公文と学研を左右に分けてメリット・デメリットを整理します。
| 公文 | 学研 | |
|---|---|---|
| メリット | ・毎日宿題があるので学習習慣が身につく ・プリントの反復で基礎がしっかり定着 ・学年にとらわれず先取り学習ができる | ・宿題量が公文の半分程度で負担が軽い ・プリント+教具、遊びを交えて楽しく学べる ・少人数制で先生が寄り添ってくれる |
| デメリット | ・宿題が多く親のサポートが必須 ・「黙々と取り組む雰囲気」が合わない子もいる ・先生との相性が子どものやる気に直結する | ・反復量は公文より少ない ・教室によって雰囲気や先生の方針に差がある ・小学生からは週2回になるため通塾負担が増える |
通わせる前にチェックしたいこと
体験談を通じて強く感じたのは、「親の思い」だけでなく「子どもの気持ち」がとても大切ということです。
公文も学研も良い教材と仕組みがありますが、続けられるかどうかは子ども次第。
習い事を選ぶときに、親としてチェックしておきたいポイントをまとめました。
- 宿題の量を家庭でサポートできるか?
毎日プリントをする習慣が親子に合っているか確認 - 通う回数・送り迎えが無理なくできるか?
生活リズムや親の働き方に合わせられるかどうか - 先生との相性はどうか?
子どもが「楽しい」「また行きたい」と思えるかが一番の判断材料
 | 【中古】 3歳 はじめてできたよ ギフトセット(4冊入り) (学研の幼児ワーク) 価格:10501円 |
 | 学研の幼児能力開発シリーズ 三角鉛筆 はじめてのセット 4B おけいこノート かず 入門セット プレゼント お祝い 名入れ 学研教育総合研究所監修 価格:1045円 |
まとめ
公文も学研も、それぞれに良さがあり、子どもの性格や家庭の状況によって合う・合わないが大きく変わります。
実際に両方を経験したからこそ、「どちらが正解」というよりも、子どもに合った学び方を見つけることが一番大切だと感じました。
わが家が習い事を選ぶときに大事にしているのは、次の3つです。
- 子どもが「やりたい」と思えること
- 親も無理なく続けられる環境であること(送り迎え・宿題のサポートなど)
- 勉強だけでなく、楽しく通える雰囲気があること
この3つを意識するだけで、習い事は「ただ続けるためのもの」ではなく「子どもが自分から学びたくなる時間」に変わると思います。
もしこれから公文や学研を検討しているなら、まずは体験授業に行ってみて、子ども自身がどう感じるかを見てあげるのがおすすめです。
親の希望だけで決めるのではなく、子どもの表情や言葉に耳を傾けることが、楽しく長く続けられる習い事選びにつながると実感しています。
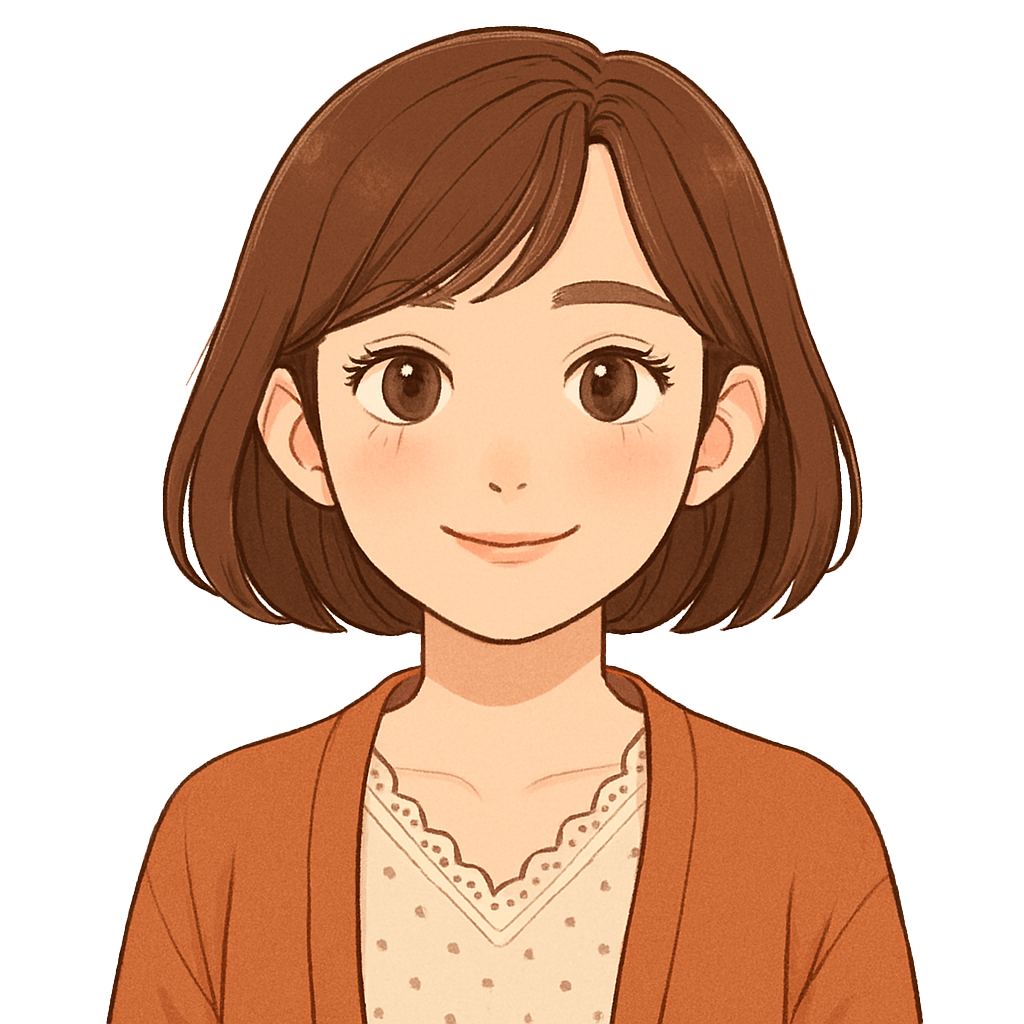
この記事を書いた人:彩月いろは
ママ目線で、気軽に楽しめる情報をゆるっとお届けします♪




